
県立琴平高校の生徒有志が、阪神大震災の復興住宅に住む被災者らと文通を続けている。復興住宅で孤独死が相次いだ問題を知った生徒らが18年前、「自分たちにできることを」と始めた。日々のたわいもない出来事や趣味に、相手を気遣う言葉が並ぶ手紙は、コロナ禍でも途切れることなく届き続けた。(黒川絵理)
今月10日、同校の教室で生徒約10人が集った。有志で作る同好会「とらすとK」が、毎月1回開く「神戸に手紙を書く会」。「香川でも雪がちらつきましたが、体調いかがですか」「年賀状をありがとうございました」……。どの生徒も真剣な表情で便箋に向かう。
2年の女子生徒(16)は、神戸市の女性に宛て、修学旅行の思い出や年末年始の過ごし方をつづった。女性は以前、「若い時は今しかないから、
■ □
活動は2005年、仮設住宅や復興住宅で転居を繰り返し、顔見知りがいないまま孤独死する問題を知った2人の生徒が始めた。同好会の名前には、英語で信頼を意味する「トラスト」と、神戸と琴平の頭文字の「K」を取った。「神戸と琴平を信頼で結ぶ」という願いをこめたという。
「拝啓 神戸の方へ」。最初はそんな宛名のないの手紙を、復興住宅で見守り活動をしていたNPO「よろず相談室」(神戸市)に託し、高齢者らに配ってもらった。
同NPOの牧秀一さん(72)は「届くのは公共料金の請求書だけという被災者が多い中、手書きの手紙で『私はあなたのことを気にしています』というメッセージが届くことは格別だった」と話す。
やがて返信が届くようになり、文通が始まった。生徒が卒業すれば、新入生が文通相手として引き継ぐことを繰り返し、今、12人の生徒が神戸の約60人とやりとりを続ける。東日本大震災や熊本地震の被災者とも文通している。
毎年2回程度、神戸を訪問し、交流会を開いたり、直接相手宅を訪ねたりもしてきた。コロナで20、21年度は訪問は途絶えたが、その間も文通は続いた。
□ ■
昨年7月、生徒らは2年ぶりに神戸を訪ね、復興住宅の集会所で交流会を開いた。生徒の乗ったバスを、文通相手らは外で手を振って出迎えてくれたという。
神戸市中央区の須藤雅樹さん(65)は、震災で自宅が半壊、復興住宅に移り住んだ。2年前に転居した後も復興住宅で茶話会などの交流活動に取り組んできたが、コロナ禍で自粛を余儀なくされた。
だが、その間も届いた手紙に「香川からも、関わりつづけてくれる若い子がいる。こちらも頑張らなければ、と励まされるような気持ちだった」という。昨年春以降、交流活動を再開しているという。
活動してきた生徒はほとんどが震災後に生まれた世代。今月13日、メンバーは障害を負った被災者や、自宅を失い転居を繰り返してきた高齢者が語るDVDを視聴した。1年の女子生徒(16)は「たくさんの人が大変な思いをしたことがわかった。手紙を楽しみにしてもらえるなら、ずっと続けたいと改めて思った」と話した。
とらすとKは昨年度、「高校生主体で被災者支援活動を続け、文通という文化を大切にしている」として、県のボランティア大賞を受賞した。牧さんは「被災者の高齢化は進み、孤立感は年々深まっている。自分に宛てた手紙の特別感は増している。これからも活動を続けてほしい」と話す。
からの記事と詳細 ( <阪神大震災28年>被災者気遣う 文通18年 - 読売新聞オンライン )
https://ift.tt/BdGsMUH





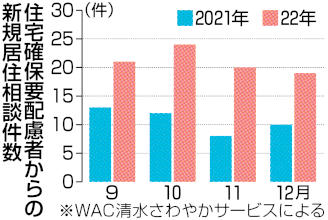


 いい茶
いい茶
