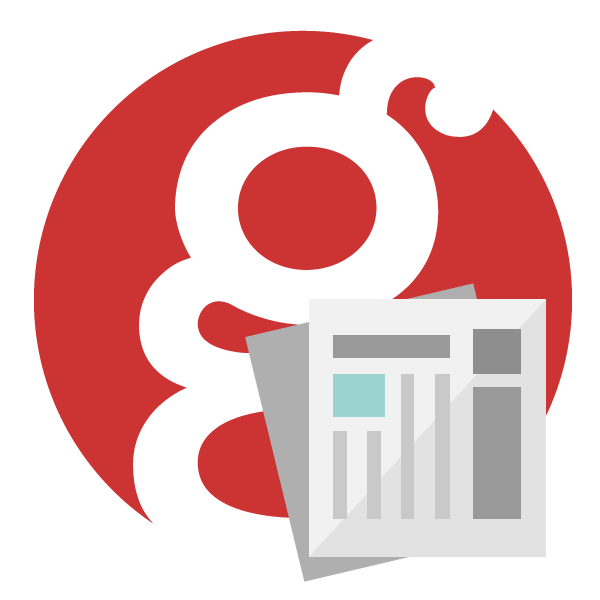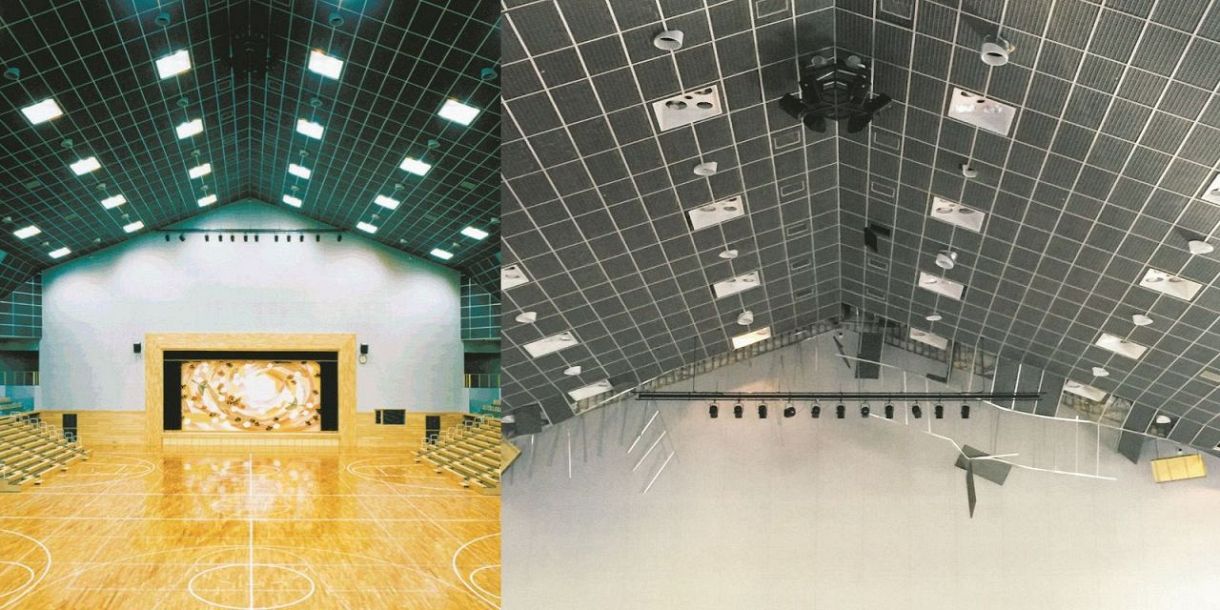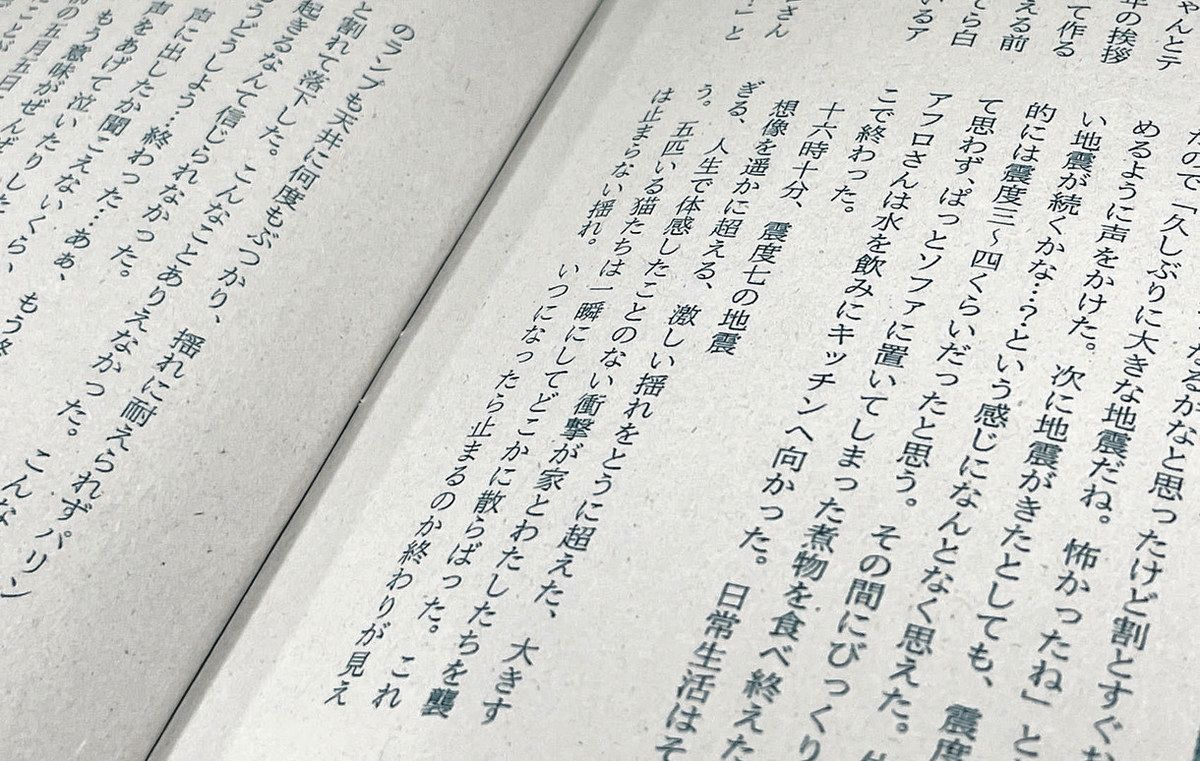taritkar.blogspot.com
地震、台風、豪雨などの災害はいつやってくるか分からない。防災グッズも揃えておきたいところだが、何をどのような基準で選べば良いのだろうか。
被災者の支援や防災の普及活動に取り組む、NPO法人「ママプラグ」の理事・冨川万美さんによると、災害時は普段と環境が変わるため、想定していないことで苦労したり、意外なものが役立ったりするともいう。そこで、支援活動を通じて感じた“あってよかったもの”を中心に聞いた。
食事は「手軽さ」を重視しよう
冨川さんによると、災害時にまず必要となるのは「食事」「水」「災害関連の情報」。この3つはどれが欠けても命にかかわるため、優先して対策してほしいという。
ポイントは、電気・ガス・水道などのライフラインが止まる可能性を想定しておくことだ。食事は災害用の非常食でなくとも、常温で手軽に食べられるものがあれば備えになる。
栄養やカロリーを摂取できる食べ物を備蓄しよう(画像はイメージ)
この記事の画像(7枚) ・魚や肉の缶詰
栄養やカロリーが摂取できる、こうしたものを備蓄しておくと良いだろう。カセットコンロ・ガスボンベがあるなら、フリーズドライ・インスタント食品もお勧めだ。疲れて心細くなったとしても、温かい食事があると気持ちも変わってくる。
「停電が続くと冷蔵庫にある食材は傷む前に消費していかなければなりません。カセットコンロはそうした時も役立つので、持っておいてほしいですね」(以下、冨川さん)
水なしで衛生環境を整えるアイテム
水は生きるために欠かせないが、災害時も一人あたり、少なくとも1日3リットルが必要とされる。断水することを想定し、最低でも家族が3日、できれば1週間暮らせるくらいの量はペットボトルで買い置きしておこう。
水は背負うと持ち運びやすい(画像はイメージ)
給水所で水の配給を受けるなら、自宅まで運ぶことも必要になってくる。大量の水を運ぶのは重労働となるので、載せて運べる「台車」や背負える「ウォーターバッグ」があると便利だ。
断水すると、トイレやシャワーが使えなくなることも忘れてはならない。汚れや臭いが気になってくるので、次のような“水なしで衛生環境を整えられるもの”を揃えると心強いという。
・非常用トイレ
「このほか、赤ちゃん用の『おしりふき』もお勧めです。成分が肌に優しいので、大人も子供も安心して体全体を拭くことができますし、避難所にも持っていきやすいです」
充電切れを「電池式」バッテリーで阻止
災害時は状況が短時間で変わることもあるため、正確な情報を知っておくことが大切だ。そこで役立つのが「スマホアプリ」。災害情報が届くもの、避難所の場所が検索できるもの、ラジオが聴けるものもあるので、平常時にダウンロードして使ってみるようにしよう。
乾電池で充電できるバッテリーがあれば、停電にも備えやすい(画像はイメージ)
また、長期間の停電が起きたり、スマホのバッテリー残量が少ない状況で避難したりすることもあるかもしれない。充電切れで情報の入手ツールを失うことがないよう、乾電池で充電できる「電池式」バッテリーを用意するなど、いつでも充電できる備えをしておこう。
小さな子供と動くなら「おんぶ紐」
このほかにも、災害時に助けとなるものはいろいろある。例えば、赤ちゃんや小さな子供がいる家庭で役立つのが「おんぶ紐」や「抱っこ紐」。親は子供を支えつつ、両手を空いた状態にできるので動きやすいという。普段から使い慣れている製品を、災害時にも有効活用してみよう。
手元を明るくするランタンがお勧め(画像はイメージ)
また、夜間の停電に備えて持っておきたいのが「ランタン型のライト」。手元を広く照らせるので自宅が散らかっていたり、外を歩いたりする時に重宝するという。
そして見落としがちなのが「現金」の大切さ。災害時は電子マネーやクレジットカードが使えなくなることもあるので、1~2万円分くらいの紙幣と小銭は用意しておこう。
防災リュックには思わぬ落とし穴も
もしもの時に持ち出せる「防災リュック(非常用持ち出し袋)」は便利だが、ちょっとした落とし穴もある。市販のセットを購入して満足してしまい、有効活用できないケースが目立つというのだ。
「触ったことがなくて使い方が分からなかったり、どこかにしまいこんだまま、取り出す余裕がなかったりすると聞きます。いざという時に使えなければ意味がないので、試してみたり、必要に応じて中身を見直したりしてほしいですね」
防災リュックは手作りも選択肢に(画像はイメージ)
余裕があるなら“オリジナル防災リュック”を手作りするものアリ。赤ちゃんがいる家庭は「ママバッグ」、子供がいる家庭は「旅行バッグ」の延長線で揃えると災害に備えやすいという。
【赤ちゃん連れ向けのお勧めアイテム例】
【子連れ向けのお勧めアイテム例】
リュックは物を入れると重くなるので、背負った時の歩きやすさも考えて選んでみよう。
災害時は物資がすぐ手に入らない可能性もあるので、日頃から備えておくことが大切だ。皆さんの家庭でも防災グッズや備蓄を見直してみてはいかがだろうか。
冨川万美さん
冨川万美
FNNプライムオンラインのオリジナル特集班が、30~40代の仕事や子育てに忙しい女性に向け、毎月身近なテーマについて役立つ情報を取材しています。
Adblock test (Why?)
からの記事と詳細 ( 災害時に「あってよかった」!被災者の声から選んだ子連れ避難に役立つ防災グッズと備蓄品|FNNプライムオンライン - FNNプライムオンライン )
https://ift.tt/qW4DNxV

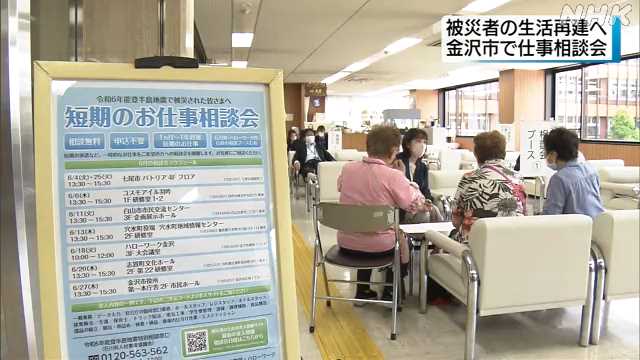




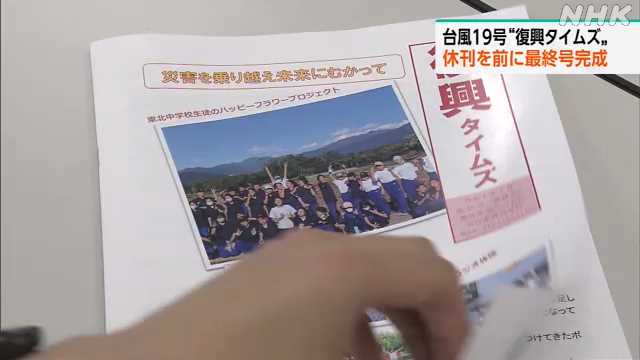







:quality(70)/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/2AOKRMF4XBMCLOU5OS7F3J2NAI.jpg)